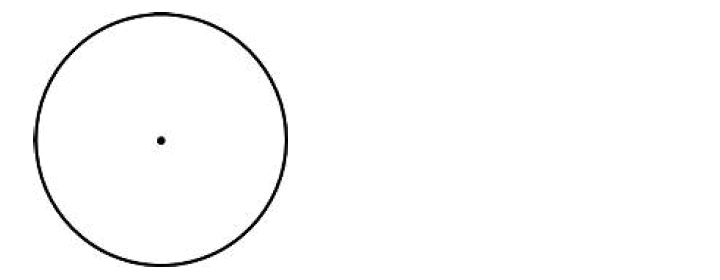政治とは基本的に欠乏や不平等、不公平(比較)、への是正などを動機に、
多数決の原理で動く。
芸術性はそれとは全く別の動機で動く。
欠乏では無く充足、満足感、至福感を原動力にして動く。
一般的に考えればハングリーな、状況が切迫した方が必死なので強い。
至福感で満ち足りたものが、
どうして何かと対立して、そして相手を組み伏せることなど出来るだろうか?
愛を原動力とした者が、何かを圧倒して、勝つことなど出来るだろうか?
そもそも〝誰かに勝つ〟という動機を持つのだろうか?
瞑想的な視点はA地点とB地点との比較を超えた垂直の視点を意味する。
それはピラミッドの上の「ものみの目」だ。
宗教や哲学の分野では、
「精神の高度化」といった場合、それでもなおそれは三次元的な発想では無く
まだまだ平面的な自動車レースのような視点だった。
そこに「鳥のような垂直的な飛躍」はなかった。
わずかに土着のシャーマニズムなどに細々とあったに過ぎない。
だから努力や根性やヒエラルキーといったマインドの発想を脱しなかったのだ。
「勝つ」「相手を圧倒する」という発想そのものからの脱出の中に
「圧倒的な何か」があったのだ。
水平的動機が終わったところに垂直的動機が起きる。
欠乏感からでは無く、祝祭から・・・